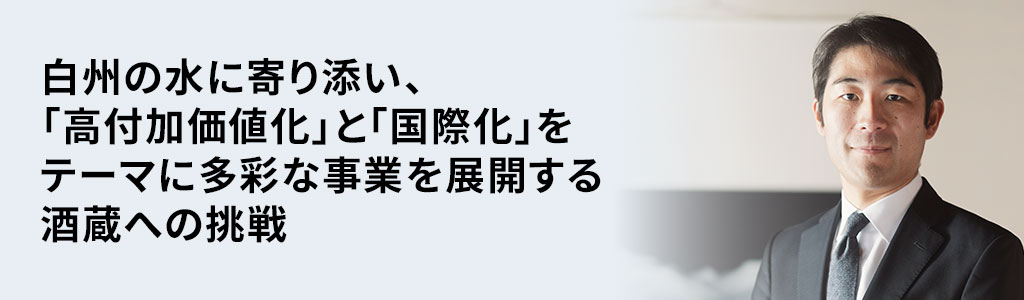ストーリー
2014年、生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目的とした地域「南アルプスユネスコエコパーク」に登録承認された甲斐駒ヶ岳の麓にあり、世界が注目する「白州」の水を用いて日本酒づくりをしている北杜市白州町における唯一の蔵元が、代表銘柄「七賢」で知られる山梨銘醸株式会社である。1750年創業という長い歴史を持つ同社は、この地がもたらす恵みとも呼ぶべき清冽な水にこだわり、水と向き合いながら真摯に酒づくりを行ってきた。現在では、伝統を継承しながらも「高付加価値化」と「国際化」をテーマにリブランディングを実施し、世界で愛される酒づくりに方向を転換。現在、日本国内にとどまらないラグジュアリーブランドを目指して多彩な事業活動を牽引する同社の代表取締役社長であり13代目蔵元の北原対馬氏に、その想いと今後の展望をうかがった。
江戸時代から続く300年の歴史と伝統、酒づくりの継承者としての自負
同社の歴史は、江戸時代の1750年、それまで長野県の高遠にて代々酒造業を営んでいた初代蔵元・北原伊兵衛光義が、江戸へと向かう際の宿場としてたびたび訪れていた白州の水に惚れ込み、甲州街道台ヶ原の地で創業したことに始まる。1880年には、明治天皇の御巡幸に際し、北原家の母屋の奥座敷が行在所(あんざいしょ)に指定されるなど、この地の歴史と深い関わりを持つ酒蔵である。
1925年には、10代蔵元の北原庫三郎が、現在に至る「山梨銘醸株式会社」を創立。甲斐駒ヶ岳の花崗岩で濾過された超軟水である白州の天然水を使った酒づくりを積極的に推進したことで、県下最大の業績を誇る酒蔵に成長。以来、同社ならびに代表銘柄の「七賢」は、北原家代々の当主に脈々と受け継がれてきたのである。この歴史を顧みれば、北原家の長男として生を受けた現代表取締役社長であり、13代目蔵元である北原対馬氏が家業を承継するのは当然の流れ。使命ではなく宿命と言えるのかもしれない。
北原氏は現在42歳。東京の大学を卒業後、アメリカの日本酒卸会社に就職。3年間ほど西海岸と東海岸で勤務した後、家業である同社に入社。代表取締役社長に就任したのは36歳と、酒蔵の経営者としてはかなり若い年代での着任だったが、アメリカでの3年間が経営者としての礎になっているという。
「アメリカでは、頑張ったら頑張った分だけ成果が出るという、近年の日本ではなかなか考えられないような経験をさせていただきました。一方で、たくさん失敗もしました。22歳から25歳までの若い日に、数々のトライ&エラーを経験できたのは本当によかったと思っています。また、大学時代には日本酒の現状に少なからず危機感を抱いていましたので、税理士講座を受講して簿記や酒税をマスターしたことも、今考えるとよい結果につながりました。私は20歳前後の頃にはすでに経営者になる自負を持っていたので、酒蔵を継承する者として何が必要なのかを考え、行動できたことが今に生きていると感じています。」


未来に向けて、13代目蔵元として掲げた会社のテーマは「継承と革新」
アメリカから帰国し、実家である同社に入社した北原氏を待っていたのは日本酒業界の厳しい現実であり、同社の経営も苦しい状況に陥っていたという。現体制を変えなければ歴史を紡いでいくことはできないと考えた北原氏は、「継承と革新」をテーマに掲げて会社の変革、リブランディングを進めていったのである。
「現状維持は衰退の始まりだと思うんです。日本酒が惨憺たる状況にあっても、会社が成長していくための選択を取らない限り、成長は見込めません。そのためには果敢に挑戦することが大切だと思うんです。それが『継承と革新』です。革新を続けていると、周囲からは『よくなったね。』という言葉ではなく『変わったね。』と言われることが多いのですけれど、私たちは変化すること自体が目的で革新を続けているわけではないんです。山梨銘醸という暖簾、ブランドを未来永劫繁栄させるために、変わらなくてはいけない時には鋭意決断して変化に挑戦することを選択しているだけなんです。」
そこで北原氏は、2014年に弟とともに変わることのない創業の精神はそのままに、同社のフィロソフィーの一部ともいえる「白州」の水に向き合う酒づくりに着手した。超軟水という特徴を持つ白州の水との対話の中で発見したのは、フレッシュで香り華やぐ、スッキリとした味わいの日本酒に適しているということ。また、酒づくりに関しても試行錯誤を繰り返しながら「吟醸づくりの原酒仕立て手法」を確立。白州の水の特徴を最大限に生かし、ワインのように食中酒として楽しまれるタイプの日本酒を開発したのである。しかし、その味わいは、長い歴史を持つ同社の代表銘柄『七賢』とは異なるものだった。
「酒蔵は地元の米と水を使い、それにふさわしい酒を醸していく。それが本来の職人なのだと私たちは理解しています。その中で、主原料を米ではなく水と定めたことにより製造戦略とマーケティング戦略が固まっていきました。結果、商品の中身からラインアップ、パッケージ、価格までオールリニューアルすることになったのですが、当初は周りから多くの非難を浴びました。『会社を潰す気か。』と。他にも、新しいお酒の特徴を踏まえて流通先や商品ラインアップを見直したのですが特にカップ酒の販売をやめると決めたときには、相当怒られました。しかし、結論から言えば売上全体が伸びる結果となり、少しずつ実績を積み重ねていくことで、私たちの考えた戦略が間違いではなかったことを認めていただけるようになりました。」
こうして、「七賢」というブランド名はそのままに、13代目蔵元によるあらたな「七賢」シリーズが同社の代表銘柄となった。だが、北原氏の挑戦はこれだけにとどまらない。「七賢」シリーズの商品数を厳選した一方で、あらたなお酒や商品を次々と誕生させたのである。


グローバル展開に向けて、ラグジュアリーブランドとしての価値を創出
同社では、2014年から2016年の約3年間をかけて商品ラインアップの変更を完了。それとときを同じくして開発を進めたのが、瓶内二次発酵製法を用いた「スパークリング日本酒」シリーズである。中でも、フランス料理界の巨匠アラン・デュカス氏とコラボレーションした「アラン・デュカス スパークリング サケ」は世界の美食家から注目を集めている。
「アラン・デュカスさんとは、ある審査会で私どもの日本酒が優秀な成績を収めたときに、ご紹介をいただいたことがきっかけでお知り合いになることができました。アラン・デュカスさんは『健康で食べ続けられるフレンチ』をテーマに掲げているのですが、彼の料理と日本酒の相性がすごくよいんですね。数年にわたるお付き合いの中、『乾杯の場面にふさわしく、世界の美食家が唸る、されども日本酒らしいスパークリング酒を作って欲しい』というオーダーを受け、2021年に開発したものになります。今、世界に輸出されている商品のひとつです。」
また、「スパークリング日本酒」同様、アラン・デュカス氏の名を冠した商品が「アラン・デュカス・サステナブル・スピリッツ」である。この商品は焼酎に分類される蒸溜酒だが、商品名にサステナブルと付けられているように、産業廃棄物として大量に処理されてきた酒粕を原料にしたものだ。
「日本酒の製造過程で副産物として酒粕ができるのですが、食の欧米化やライフスタイルの変化に伴って酒粕の消費が減っているため、お金を払って廃棄していたのですが、あらたな価値創造の機会と捉えて開発した商品になります。酒粕を蒸溜し、サントリー白州蒸溜所のウイスキー樽で3年程度熟成させた焼酎です。また、蒸溜後に酒粕の残滓が出るのですが、これは人間でも食べられるような高栄養価なものになります。その酒粕を、山梨を代表する銘柄の和牛の飼料として使っていただき、さらに牛の糞尿を堆肥化して酒米の田んぼに撒いているんです。いわゆる、アップサイクル型の生産理念のもと、取り組んでいることのひとつです。」
この他、酒粕や米糀を原材料とする発酵食品ブランド「ひとさじ糀」、米糀由来の天然成分「糀糖」を原料に用いたスキンケアブランド「COJIE(コウジィ)」の製造販売に加え、醸造所の敷地内にレストランやカフェを併設。あくまでもメインは日本酒の製造販売ではあるが、SDGsを意識した事業の多角化も実施している。


次の世代によい状態でバトンを渡すことが13代目のバトンを受け取った自分の使命
現在、同社の日本酒はヨーロッパを中心に25ヶ国に輸出されている。中でも、「スパークリング日本酒」を世界に広げていくためのマーケティング戦略を展開中なのだとか。そのひとつが、東京を含む世界7ヶ国にあるアラン・デュカス氏の各店舗で行われるペアリングディナーワールドツアーの開催である。
「アラン・デュカスさんとコラボレーションしてプロダクトを作りましたが、そこで終わるのではもったいない。フレンチのトップブランドと山梨県の日本酒メーカーであるわれわれがイーブンな立場で恒常的にプロモーションを実施することは、世界で最も認められているフレンチ料理界に日本酒が入り込んでいく大きなきっかけとなります。国内日本酒メーカーを代表してプロモーションしていきます。」
また、同社の今後の取り組みとしては、築200年以上の古民家を一等貸しの旅館として、2025年3月プレオープンを目標に建設中。この旅館はオーベルジュのような施設となり、料理とお酒を楽しめる古民家旅館がコンセプトとなっている。まさに「七賢」ブランドが目指す「高付加価値化」と「国際化」を標榜するような旅館をイメージしている。
さらに、2030年目標でオフィスと倉庫が一体型となった新工場を建設予定。すでに同社では電力をすべてCO2フリーの自然エネルギーに転換することで約510トンものCO2削減に成功しているが、新工場ではLPガスも再生可能エネルギーであるグリーン水素に置き換える予定だという。このように日本酒づくりのみならず、マーケティングも含め多角的な事業展開を精力的に行っている北原氏。そのモチベーションの源泉こそが「継承と革新」の実現にある。
「自分たちの業界をどのように捉えるか、という話を社員とも共有しているのですが、仮に1,300社ある日本酒業界の1社だと捉えると、日本酒マーケットがどんどん縮小していることを考えると明るい未来をイメージできません。私もそう捉えていたら、たぶん家業を継承できなかったと思います。そうではなく、アルコール業界として捉えれば5兆円規模の中の1社になる。もしくはエンタテインメント業界として捉えれば何十兆、何百兆円規模の中の1社であると。そして、マーケットを日本だけではなく、世界にも目を向けたなら随分と目線が変わり、未来も明るくなり、成長戦略を描くこともできます。だからこそ今が大切なのです。私は13番目のバトンを紡いだリレー走者でしかありません。私がやるべきことは、14番目、15番目にバトンを受け取る人に、いかによい状態でパスできるかだと思うのです。そのためには、よいブランドを構築し、よい技術を発展させて、よい従業員を引き継ぐ。それが成し遂げなければいけないことであり、私の務めであると考えています。」
長い歴史と伝統を誇る家業を継承し、次世代へと紡いでいく責任の重さは図り知れないが、北原氏の発想や言葉は常に未来へと向いている。しかも、自社の成功だけに目を向けているのではなく、日本酒業界や環境配慮、地域活性化も意識した取り組みにつながっている。同社が掲げる「継承と革新」が、どんな未来へと結実するのか。その動向に注目したい会社である。