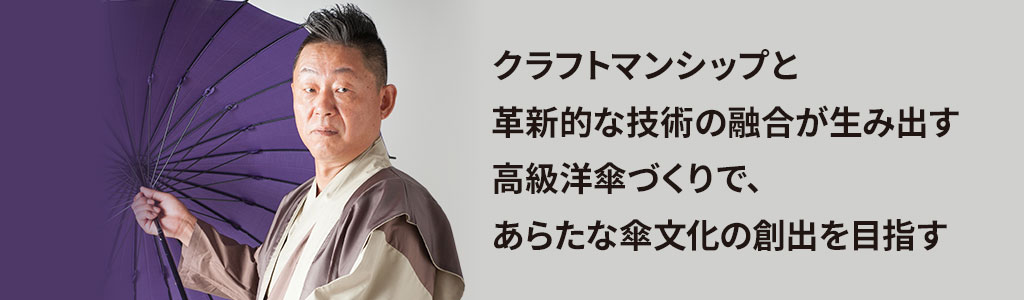ストーリー
福井県における洋傘づくりの歴史は江戸時代後期にまで遡る。以来、福井県をはじめとする北陸の地は約800社を超える傘メーカーが存在する一大生産地として知られていた。しかし、時が流れ、機械張りの安価な傘のニーズが高まるとともに、海外に生産がシフトしたことで、ほとんどのメーカーが廃業を余儀なくされた。日本の傘づくり文化が危機的な状況を迎える中で、「他社が真似できない傘づくり」をコンセプトに事業を展開し、高級洋傘メーカーとして国内外にその名を馳せているのが、株式会社福井洋傘である。地元の福井県産素材と革新的な技術を生かした独創的な傘の製造で注目を集める同社の代表取締役社長・橋本肇氏に、ものづくりへのこだわりや今後の展望についてお話をうかがった。
日本の洋傘づくりの歴史を守るため、逆転の発想で「真似をされない」ものづくりに挑戦
橋本氏の父親であり、県の農業委員を務めていた先代が株式会社福井洋傘を創業したのは1972年のことだった。大阪の洋傘メーカーの下請けから事業をスタートさせた同社は、高品質な傘づくりが高い評価を受け、順調に事業を進めていた。しかし、大資本のメーカーが製造する安価な傘が主流となり、生産拠点も海外へとシフトしたことで、福井県内の洋傘業界は衰退の一途をたどることとなった。そんな中でも、高品質な傘の製造に特化していた同社は最後まで踏みとどまっていたが、時流には抗えず先代社長は廃業を考えていたという。その状況を目の当たりにした橋本氏は、それまで勤めていた地元の放送局の関連会社を退職し、家業を継ぐ決意をする。バブルが崩壊し、高級品が売れない時代と言われていた1989年のことだった。

「うちが廃業してしまうと、日本における洋傘づくりの歴史が途絶えてしまう。だから、やめるわけにはいかないと先代に伝えたんです。腹をくくって、背水の陣でいくしかないと。幸いなことに、うちの技術力は評価されていましたので、あえて高級傘で勝負しようと決めました。周囲からは『今のご時世、そんな傘が売れるはずない。』と言われましたが、私の考え方はむしろ逆。全員が『売れない。』と言うものは売れると思っているんです。他社が『儲からないから、真似する意味がない。』と思うような傘づくりをしようと考えたんです。それともうひとつ、例えば身体が不自由などの理由で、流通している傘が使えなくて困っている人たちのために傘を作ればいいのではないかと。どんなに赤字でも潰れない会社がある一方、どんなに儲かっている会社でも潰れるときは潰れる。それは、世の中がその会社を必要としているかどうかだけだと、私は思っているんです。だから、世の中に必要とされる会社にするために、必要とされる仕事をしていこうと考えたんです。」
同社は、高いデザイン性と機能性を併せ持った高級洋傘を製造する一方、まだユニバーサルデザインという言葉がない時代から、身体が不自由な人でも使いやすい傘の開発を続けてきた。その一例が、試行錯誤しながら約20年の歳月をかけて完成した、国際意匠も取得している利用しやすい形状と革製の輪が付いた「手元」。高級な傘をつくるだけではなく、困っている人に必要な傘をつくるという橋本氏の信念が結実したのである。

独創的なものづくりを支えているのは、「伝統」を次世代へとつなぐ意志
同社のものづくりの最大の特徴は、福井県産の素材と技術を活用した全工程手づくりにある。「繊維王国」とも称される福井県には多くの繊維メーカーがあり、商品によっては傘用生地を地元の繊維メーカーと共同開発する。また、鯖江市の眼鏡フレームの製造技術は傘の骨づくりに生かされ、持ち手と傘の頭の部分は漆塗りの伝統技術の河和田塗りで仕上げられている。
「福井の地場産業である繊維・眼鏡・漆器を集めると傘になる。弊社の傘は、さながら福井の物産品のような商品だと自負しています。また、傘を軽量化しようと骨の数を減らすのが主流の中、弊社ではデザイン性の観点から24本まで骨の数を増やして看板商品の『蛇の目洋傘』を作っています。骨の数を増やしても重さに影響しない傘づくりは他の会社は真似できないでしょうし、真似したところで本物はつくれない。そのぐらいの思いと誇りを持って傘をつくっています。」

また、もうひとつの特徴が、最新の機械を用いた素材開発である。一般的な傘は骨にステンレスが使用されているが、同社では軽量かつ高強度のカーボンや炭素繊維を用いており、これらは自社工場で製造したもの。また、多様な形状の木製「手元」や石突き(洋傘の頭部)は小ロットでも製造可能な特許技術の切削加工マシン「3Dターニングマシン」を使って作られている。これもまた自社保有である。手づくりにこだわりながら、最新の機械設備を用いて素材を開発する。相反するようにも思えるが、そこには橋本氏の「伝統」に関する考え方が大きく影響している。
「弊社は伝統をつくっているのであって、古典はやっていないんです。昔から脈々と続いているものを受け継ぎ、技術開発がなされていないのが古典。だから廃れていってしまう。伝統というのは、今まで良いとされてきたものに、最新技術を取り入れて次の世代に渡すもの。それが伝統だと私は解釈しています。だから、うちは伝統をつくっていきたいと思っています。」
曹洞宗総本山永平寺御用達の『蛇の目洋傘』や、大島紬や友禅などの職人技による生地を使った商品を製造する一方、独創的なものづくりに挑む根底には、橋本氏が考える「伝統」の継承という想いがあるのだ。

徹底的な顧客志向を貫き「一生もの」の洋傘を提供
同社の革新的な商品のひとつが、「濡れない傘」をコンセプトにした『ヌレンザ』である。地元の繊維メーカーと、優れた撥水性と耐水性を兼ね備えた超高密度のポリエステル生地を約1年かけて共同開発して誕生した『ヌレンザ』は、高級自動車ブランドの関連グッズにも採用されるほど、機能性と高いデザイン性が評価されている。この『ヌレンザ』も、「雨が降ったとき、電車内や車内などで、傘の水滴で服や靴が濡れて困る。」というユーザーの声がきっかけでできた、同社の顧客志向を象徴した商品である。

同社の傘は手づくりであるがゆえに大量生産ができない。しかも、さまざまなアイデアを熟考しながら、時間をかけて理想の商品をつくっていくという。それだけに、ひとつひとつの商品に対する同社のこだわりや想いも強く、それが、単なる雨具や消耗品ではない「一生もの」の傘を愛用品として求める人たちに支持される所以でもある。そんな同社の商品への想いは、メンテナンスなどのアフターケアにも見てとれる。
「残念なことに、日本はものづくりの国だったのに衰退してしまっている。それに伴い、いろいろな材料が手に入りづらくなっています。弊社の商品は貴重な材料を使っていますが、私たちはお客さまに貴重な材料をお預けしているというふうに考えているんです。その材料をお預けしておいて、後で『こういうふうに変えたい。』という希望があれば、我々が手直しをしてその傘を使い続けてもらうことができる。やはり、自分が手塩にかけてつくった傘は自分の子どものような存在で、大事に使っていただけているか気になりますしね。それもあって、弊社では全国の百貨店や百貨店の催事で商品を販売しているんです。百貨店はアクセスのよい場所にありますから、お客さまも足を運びやすいはずですし、百貨店もマージンが取れる。まさに三方良しの関係が成り立つしくみを作ることができました。」
このように徹底した顧客志向に基づく商品開発とサービスを行っている同社が、近年の温暖化や紫外線対策を考慮して日傘を新発売する。同社のラインアップには雨傘と日傘兼用の『棗(なつめ)』という商品がすでにあるが、新商品は日傘専用となっている。その理由は、兼用傘を販売しているメーカーとの差別化に加え、兼用傘は風を通さないため暑く感じる人がいることを考慮したのだという。兼用傘を暑く感じるのは少数の意見、とは橋本氏の弁だが、その要望に応えるところが同社の顧客志向であり、ものづくりへのこだわりなのだと感じる。

福井県の伝統工芸技術が集積する生産拠点「傘村」の実現に向けて邁進
福井の地にこだわり、福井産の素材や技術にこだわる橋本氏が現在構想しているのが、自社の所在地である旧棗村に傘の発信・生産拠点となる「傘村」をつくることだという。
「当初は、弊社の開発者や技術者を広く募ることを考えていたのですが、そうではなくすでに技術を持った職人さんに場所を提供し、好きなように活動してもらいながら、弊社の商品づくりにも参加してもらえればと思っているんです。福井県の伝統工芸に携わる職人さんたちが集積する場所のようなイメージですね。この場所に来れば、いろんな職人さんの仕事が見られる。それが『傘村』の根幹になると思っています。」
北陸新幹線が福井県の敦賀まで延伸したことで首都圏からのアクセスがよくなり、今後は観光客の増大も予想されるが、まだまだ福井県の認知度は低く、福井県人であっても旧棗村を認知していない人が多い、と橋本氏は言う。過疎化が進む地域に「傘村」ができることで、流行やファッションに敏感な若者や、日本の伝統文化に関心のある外国人が集まり、多くの人に福井県、そして棗村が認知されるような場所にしたい。本人曰く、「途方もない話」だと言うが、常識にとらわれない逆転の発想と行動力で事業を拡大してきた橋本氏だけに、決して夢物語では終わらないのではないか。いや、夢物語で終わらせないために応援したくなる魅力が、橋本氏と福井洋傘にはあると感じるのだ。