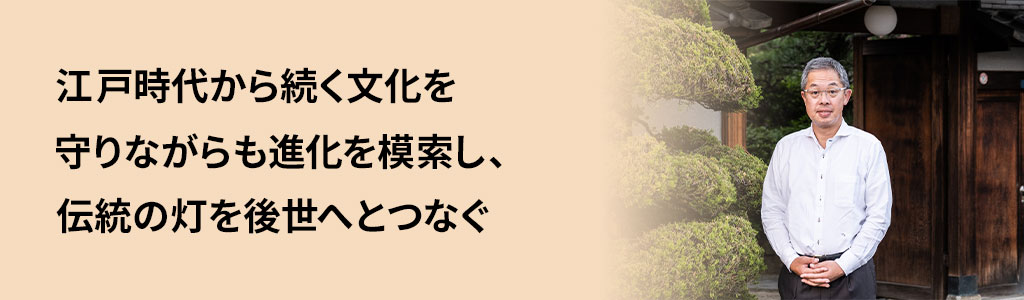ストーリー
結婚式などのお祝い事や神事にて、大きな酒樽を用いて行われる「鏡開き」。古くから、喜びの場面を演出する日本独自のセレモニーとして継承されてきた。このときに使われる杉の酒樽を「菰樽(こもだる)」といい、酒の銘柄や祝いの文字などを記し、樽を巻いている藁(わら)製の部材を「菰縄(こもなわ)」という。もともとは、酒樽を船で輸送する際の緩衝材として誕生した「菰縄」だが、酒の銘柄がわかるように、菰に商標や酒名を記した当時のデザインをそのままに、今でも使用されている。日本を代表する酒どころである伊丹・灘(兵庫県)に近い、尼崎市の伝統産業である「菰樽」づくりを120年余にわたって守り続けている株式会社岸本吉二商店。伝統の灯を絶やすことなく後世につなぐため、オリジナル商品の開発や海外展開などにも挑戦する同社の取り組みとその想いを、4代目社長の岸本敏裕氏、社員の岩岸克幸氏にうかがった。
廃業の危機を乗り越え、日本を代表する「菰縄」のつくり手へ
農業のかたわら、農家から菰縄を買い集めて蔵元へ納める仕事を行っていた創業者の岸本吉二氏が、今から約120年前の1900年に「岸本吉二商店」を創業。本格的に菰縄の製造を手がけるようになり、順調に事業を展開していた同社に危機が訪れたのは戦時中のことだった。日本酒の原料である米不足が深刻化するなど、戦争の影響から菰樽は製造中止に追いやられ、休業を強いられてしまった。しかし、そんな苦難を乗り越え、同社は戦後の1949年に復活し、事業活動を再開したのである。

「私が聞いた話によると、戦時中は休業と言うよりもほぼ廃業に近かったのかなと思います。そんな中、1949年の8月に、取引のあった蔵元から『もう一度、菰縄をつくってほしい』と依頼されたことをきっかけに、事業を復活させたそうです。ところが、その年の10月に社長だった私の祖父が事故で他界してしまったため、曾祖母と当時まだ大学生だった私の父が商売を引き継ぐことになったのです。戦後復興のなかで菰樽の需要も生まれ、全国の蔵元さんや醸造機器などを取り扱う代理店に事業再開の連絡を入れたことで多くの注文をいただくことができました。いち早く事業を再開させたことが功を奏して、今につながっているのだと思います。」
と語る現社長の岸本氏は、大学卒業後、大手ウイスキーメーカーの営業職経験を経て、1988年に同社に入社し、1999年に4代目社長に就任。日本酒需要の低迷に伴い業績が右肩下がりを続けるなか、「今、われわれが守らなければ、残らない未来がある」という強い信念のもと、さまざまな取り組みに挑戦し、業績を回復させていった。

伝統を守る使命感が生み出した個性的なオリジナル商品の数々
岸本吉二商店の事業の柱となっているのは、創業以来変わることなく蔵元から受注する「菰縄」づくりである。かつて、阪神間には10社ほどの菰縄のつくり手企業があったが、後継者不足や需要の低迷などから廃業を余儀なくされる会社が相次ぎ、現在は同社を含めて2社が残るのみとなっている。同業他社が廃業するなか、同社はWEBサイトによる情報発信や、オリジナル商品を開発し自社で販売するという取り組みに注力し、業績を向上させていった。
オリジナル商品開発の原点は、1963年に誕生した1.8リットルの「ミニ菰樽」である。お歳暮用に陶器製の小さな菰樽を販売したいという取引先の依頼を受けて誕生した同商品は、全国の蔵元から注文が入り、ヒット商品になったという。
「当時は、お歳暮商品としてビールよりも日本酒人気の高い時代だったこともヒットを後押ししたのだと思います。ただし、陶器製は大量生産が難しいことから1980年頃に容器をガラスに替えて、300ml、900mlとより小さいサイズのミニ菰樽を発売するようになりました。」(岸本社長)

同商品は国土交通省主催の2006年「魅力あるおみやげコンテスト(現在は名称を変更)」の食品部門で金賞を受賞。近年は訪日外国人がお土産用に購入するなど、発売から60年を迎えるロングセラー商品となっている。
また、2003年には、卓上サイズの「ミニ鏡開きセット」を発売。日本の伝統文化である鏡開きを人生で一度は体験してほしい、という想いから開発した商品である。
「当時、菰樽の需要についてホテルや酒販店のかたに話を聞く機会があったのですが、結婚披露宴でも菰樽を使う人が減ってきていることから『このままだと忘れられるかもしれないね』と。ひとりでも多くの人に鏡開きを体験していただきたい、菰樽を知らない人に面白いね、と思っていただきたいという想いで開発したのが『ミニ鏡開きセット』です。自宅でのお祝い事やパーティで使っていただくことを考えてつくったのですが、ブライダル業界のかたが、披露宴でのキャンドルサービスの代わりに鏡開きサービスを行うことを提案されたのを機に売上が向上しました。その使い方は想像していなかったといいますか、発想にありませんでしたから、うれしい驚きでしたね。」(岸本社長)
現在、同社では外部のデザイナーとのコラボレーションで商品のバリエーションを増やし、自社のECサイトでの販売も行っている。これもまた、「伝統の灯を絶やすことなく、次の世代へとつないでいく」という同社の想いを形にした取り組みのひとつである。

伝統文化の継承者として「菰樽」の存在を国内外に発信
菰樽づくりを通した日本文化の伝統承継と発信の取り組みは、国内のみならず海外でも展開されている。最初の取り組みは2013年のこと。ニューヨークで開催されるアメリカ最大規模の見本市「NY NOW」への出展だった。
「この時は、神社に奉納されているような通常サイズの『飾り樽』や『ミニ鏡開きセット』を、JETRO(日本貿易振興機構)が支援するジャパンパビリオンに展示しました。その際、即決で『ミニ鏡開きセット』の注文をいただいたのですが、リピートがなく1回限りの取引がほとんどでした。ただ、初めて見るかたであっても『飾り樽』がトラディショナルな商品として認識されることがわかったのですが、それと同時に海外の人には家具的な商品に映ったようなのです。それならば、『菰樽』を用いて家具的な商品をつくれないかと考え、2回目の海外展開に挑戦しました。」
と語るのは、製造部門以外の総務的な業務全般を担当する岩岸克幸氏。2014年に中小企業庁の「JAPANブランド育成支援事業」に選出されたことで資金援助を受け、「菰樽」をテーブルやイスにリノベーションするインテリアプロジェクトを牽引した人物でもある。その岩岸氏が2回目の挑戦と語ったのが、2014年にニューヨークのギャラリースペース「RESOBOX」で現地のバイヤーやメディアを招いたお披露目会を含む3週間の展示会である。

「家具業者や外部のデザイナーさんにも参加いただき、テーブルタイプの物やイスとしても利用できる『菰樽』を出展したのですが、やはり継続的な取引には発展しませんでした。その経験から、費用をかけて海外の展示会に出展するよりも、海外向けの英語サイトを充実させることで、本当に『菰樽』に興味のあるかたと直接つながる方法へと転換しました。これまでに問い合わせから契約に至ったケースが何件かありますが、売上規模から言うと正直まだまだですね。ただ、事業のあらたな軸を何本か用意する必要性は感じていますので、海外向けの販売は今後伸ばしていきたい領域のひとつですね。」(岩岸氏)
海外に意識を向ける一方で、日本の伝統的な「菰樽」づくりが途切れてしまわないよう、同社では稲わら文化を伝える取り組みにも力を入れているという。
「阪神間に限定されたものではありますが、イベントで『菰縄』を巻く実演依頼を受けることがよくあるんですね。多くのかたに『菰樽』を知っていただくチャンスでもありますので、可能な限り対応させていただいています。また、市の教育委員会の外部団体からの依頼で、授業の一環として小学校で『菰樽』荷造りの実演と地場産業の歴史の講話を行っています。このような後世に向けての取り組みに関しては、できる限り参加するようにしています。」(岩岸氏)
また、兵庫県神戸市をベースに活動する国際NPO法人「Peace&Nature」のパートナーとして、地域の里山や森林保全活動を実施するSDGsアクション ワークショップにも参画。
同社が契約している神戸市北区大沢町の農家の田んぼにて、酒米・山田錦の稲刈り体験や「菰樽」の素材である菰織り体験などを実施している。こういった活動も、今や2社だけになってしまった「菰縄」のつくり手の1社である責任感と使命感が原動力となっているのだという。
全国各地の伝統産業が職人の高齢化や後継者不足という課題を抱えているが、同社には伝統文化と技術を継承する若き職人たちがいる。その熱き想いと未来に期待を寄せたくなる会社である。