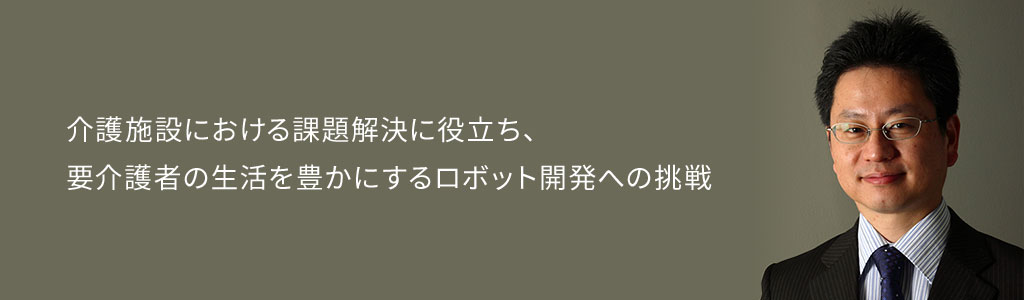ストーリー
産業用ロボット、軍事用ロボット、身近なところでは掃除用ロボットやペットロボなど、さまざまな種類や形態があるが、私たちがロボットと聞いてイメージするのは、二足歩行ロボットだろう。かつては、SF作品中に登場するフィクションの存在でしかなかったが、今や現実化しつつある。その一翼を担う企業が、量産型二足歩行ロボットの開発と販売において、世界的に見ても先駆的な存在のヴイストン株式会社である。同社は、ロボット研究者である大阪大学の石黒浩教授の特許技術を事業化することを目的に2000年に設立。石黒教授が開発した全方位センサの製品化からスタートし、2003年からロボット関連技術を事業化し、同年に二足歩行ロボットと子供サイズの台車移動式ロボットの販売を開始した。以来、コミュニケーションロボット『Sota(ソータ)』や『CommU(コミュー)』、CMや映画でも使われた大型二足歩行ロボット『Vston Tichno(ヴイストンティクノ)』をはじめとする各種ロボットを世に送り出してきた。そんなヴイストンが現在取り組んでいるのが、ロボットが介在する介護事業者向け事業である。新規事業の内容、あらたなチャレンジへの思いを、代表取締役の大和信夫氏にうかがった。
社内の技術者が趣味で作ったロボットが、
主力事業となり会社を成長させた
ヴイストン株式会社は、石黒浩教授が当時在籍していた和歌山大学発のITベンチャーとして、関西の中堅企業家グループの支援を受けて設立した。しかし、代表取締役の大和氏は、このグループ内のメンバーだったわけでもなければ技術者でもなく、起業準備を進める無職の状況だったという。
「2000年の4月に関西の中小企業団体が企画した海外視察に参加したのですが、その旅行でヴイストン株式会社の出資者となる日本エルエスアイカード株式会社の大木社長と懇意になり、私が考えたビジネスプランを見せて相談する中で、新しい会社の手伝いをしないかと話をいただいたんです。当初は営業のお手伝いという話だったのですが、5月に関係者が集まる席があり、そこで『お前が社長をやれ』と言われまして(笑)。石黒先生の開発した技術は非常に魅力的でしたし、私自身、世の中を変えていくのはテクノロジーだと考えていたこともあって、経営者としてマネジメントしていこうと社長を引き受けることになったんです。」
だが、石黒教授の特許技術である全方位センサの商品化には、いくつものハードルがあり事業は難航していた。そんなヴイストンに転機が訪れたのは、2003年のことだった。石黒教授の研究室出身のエンジニアであり、取締役・技術本部長を務める前田武志氏が趣味で作った自作の小型ヒューマノイドロボットを会社に持って来たところ、その完成度の高さから製品化が決定。同年10月に、二足歩行ロボットと子供サイズの台車移動式ロボットの2種類の発売を開始したところ大きな反響を呼び、ロボット事業がヴイストンの主要なビジネスとなっていったのである。

「実は、そんなに売れるとは思わなかったんですよ。ところが、あっと言う間に売れた。ロボットって意外に売れるものだと実感し、そこからロボットの事業が中心になりました。」
以来、自社開発のロボットを次々と販売する一方、企業からの受託開発も積極的に行うようになった。日清食品の『カップヌードル ロボタイマー』、ひよこちゃんロボット『HIYOBO』、デアゴスティーニの雑誌式パートワークのロボットキット『週刊ロビ』などがその一例だ。


介護施設現場に足を運び、試行錯誤を繰り返しながら
癒しをもたらす新しいデバイス「かまって『ひろちゃん』」を開発
実は、ヴイストンが介護現場向けロボットの開発に取り組み始めたのは、最近の話ではない。国際電気通信基礎技術研究所(ATR)からの依頼を受け、5年以上前から遠隔操作型アンドロイド『テレノイド』や抱き枕型コミュニケーションメディア『ハグビー』の開発を行う形で研究に協力していた。だが、研究用に開発されたロボットは高価格なこともあり、介護の現場に普及しなかったという。
「われわれ自身が介護現場との距離を詰めていかないと商品開発自体の課題が見えてきませんし、介護現場で求められることがわからないんですね。実際に介護施設を訪れて職員からヒアリングしながら試作品を作り、それを施設で使っていただきながら試行を重ね、製品化したものが赤ちゃん型ロボット「かまって『ひろちゃん』」(以下、『ひろちゃん』)です。弊社としては異例なんですが、『ひろちゃん』を商品化するまでに3年くらいかかっているんです。ただロボットを作るだけではなく、介護現場と一緒に取り組みをしているうちに3年経っていたという感じです。人任せにできないと言いますか、自分たちも介護の現場に入り込まなければ成立しないなと。介護系の商品は作っていましたが、ここまで踏み込んだケースはありませんでした。私たちにとって初の試みと言えるかと思います。」

『ひろちゃん』は、実際の赤ちゃんの笑い声や泣き声を100種類以上録音した音声が搭載されており、抱っこされたときのあやし方を内蔵の3軸加速度センサで検知し、関わり方によって声を変化させることで相手とのコミュニケーションを強めることができる。ATR深層インタラクション総合研究所が、大阪市の社会福祉法人隆盛福祉会が運営する介護老人施設で検証実験を実施したところ、入居者である老人たちが『ひろちゃん』をあやすことで癒し効果を得られることが実証されたという。
「まだまだ実験的な導入ではありますが、現場の介護士さんがすごく喜んでくれていますし、助かると言ってくれているんです。認知症高齢者が『ひろちゃん』をあやしている間は、症状が緩和される状況が見られると。その間、介護士さんは他の仕事ができるわけですから業務負担の軽減にもつながる。赤ちゃんの声に介護士さんも癒されるといった報告もあります。こういったことにも社会的意義があるだろうなとも思っています。」

『インタラクティブドール・セラピー』の確立が
大きな社会貢献につながることを信じている
2020年1月に販売が開始された『ひろちゃん』は、今後も介護施設で活用評価を行いながらブラッシュアップを続けていくという。その一方、『ひろちゃん』を有効活用するには運用の仕方がポイントだと大和氏は言う。
「昔からドールセラピーと呼ばれる人形を使った療法があるんです。子育て経験のある女性に赤ちゃん人形を渡すと、過去を思い出して癒し効果になると。ただ、それは子育て経験のある女性に限られてしまい、男性の場合は『なぜ人形遊びをしなければいけないのか』と拒絶されてしまう。なので『ひろちゃん』も当初は男性を対象から外していたんです。ところが関わり方によっていろいろな声の反応をしてくれる『ひろちゃん』は、介護施設でのテストを進めているうちに、運用の仕方次第で男性にも使っていただけることに気づいたんです。実は要介護者も社会とのつながりを求めているし、誰かの役に立ちたいと思っているんです。だから介護士さんが『これは私が大事にしている人形なんだけど、ちょっとあやしていてくれる?』とお願いして渡すと男性でも、ちゃんとあやしてくれる。中には楽しんでくれる人も出てきたんです。だから、『ひろちゃん』があればいいだけではなく、介護士さんと『ひろちゃん』、要介護者の三者の関係性、運用の仕方で『ひろちゃん』の価値が上がるんですよ。三者の良い関係を作ることで、高齢者の生活を豊かにし、介護士さんの負担を軽減できる。これが『インタラクティブドール・セラピー』として確立されたなら、ものすごい社会貢献ができるのではないかと考えています。」


社会に対する感謝の気持ち、善の発想に基づいて、自分たちが必要とするものを自分たちのプロダクトとして発表する。結果、開発された製品は、きっと社会や誰かの役に立つはず。それが大和氏の信念であり、ヴイストンの社員に共通する思いだという。時間はかかるかもしれないが、この信念のもとに開発された『ひろちゃん』は介護施設の現場において、「こころ」を感じさせるロボットとして普及する日が訪れるかもしれない。いや、その日が来ることを心から願ってやまない。