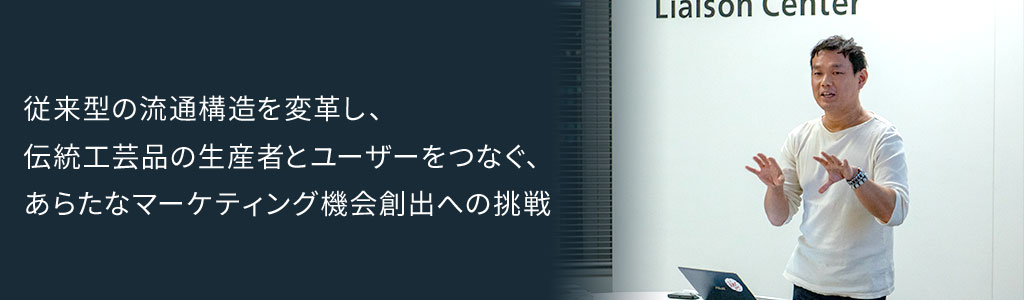ストーリー
「文化(Culture)を誇りの源泉とする世代(Generation)を創造し、あらたな社会の実現に貢献する」を経営理念に掲げる、株式会社Culture Generation Japan。
同社は、地域企業の支援や伝統工芸品事業者のプロデュースをはじめ、全国の産地を活性化させる人材育成を目的とした『JAPAN BRAND PRODUCE SCHOOL』の運営、香港企業との共同事業であるマルチレーベルショップ『HAUSTAGE』の運営など、日本の伝統工芸品とその作り手である職人を支援する事業を展開。2019年からは和食器を月額制で利用できる、唯一無二のサブスクリプションサービス『CRAFTAL(クラフタル)』をスタートさせた。年々、斜陽化が進む日本の伝統工芸品産業の課題解決に向け、革新的な取り組みを続ける株式会社Culture Generation Japan代表取締役の堀田卓哉氏に話をうかがった。
魅力的な職人たちとの出会いが、
未知のビジネスに挑む原動力となった
「もともと、伝統工芸品や昔からの技術に興味があったわけではないんです」と堀田氏は言う。彼の経歴を見れば、それもうなずける。大学卒業後、コンサルティング会社の株式会社セリクに入社し、フランス企業の技術や商品を日本のトップ企業に導入するプロジェクトに参画。その後、モナコ大学にてMBAを取得し、株式会社ホンダコンサルティングに入社し、プロジェクトマネージャーとしてグループ会社10数社の経営再建プロジェクトに携わった。約5年間の勤務を経て、2011年に株式会社Culture Generation Japanを設立。ビジネスとして日本の伝統工芸品に携わった経験などなかったのだ。
「2005年に海外留学から帰国しまして、たまたまご縁があって台東区浅草に住むことになったんです。浅草と言えば三社祭が有名ですが、自分も参加したいと思って地元町会の青年部に入ったんですよ。当時は他に参加する方法を知らなかったものですから(笑)。その頃、僕は30歳そこそこでしたが、同い年ぐらいの伝統工芸の職人さんたちがいらっしゃったんですよ。仲良くなって一緒に飲みに行ったりすると『次の世代に、日本の文化をどうつなげていくか』をキラキラとした目で話すんです。非常に魅力的で、生き方としてすごくかっこいいなと思いました。そのうち『世界に出てみたい』とか『新しいことをやってみたい』という相談を受けるようになったんです。彼らとしては、自分のやっている仕事に自信はあるけれど、具体的に何をやったらいいのかがわからない。僕は、ものづくりの専門家ではありませんが、ずっとビジネスの世界で生きてきたので、一緒にやることで何か新しい文化のようなもの、コンテンツが作れるのではないかと。ほぼ直感のようなものでしたが、社会に貢献できるような仕事がしたくて独立に踏み切りました。」

頑張っている生産者の役に立ちたい。
その思いから誕生した、和食器のサブスクサービス『CRAFTAL』
事業ドメインのひとつである産地プロデュースに関しては、過去10年間で300社以上の実績がある。ほぼすべての現場を堀田氏が訪れ、ものづくりの現場を見てきたという。
「ものづくりの現場が好きだということもあるのですが、実際に現場を見ることで感じるものがたくさんあるんです。そうすると、とても良い作品が工房の端っこでホコリをかぶって置かれていたりするんですよ。職人さん曰く『でも売れないんだよね』と。極端な言い方をすると、職人さんが作る商品には技術の粋を極めた高付加価値商品と、比較的リーズナブルな価格帯の商品の2種類なんです。ところが現在はリーズナブルな商品も売れなくなってきているうえに、流通を担う問屋の力が以前より落ちてきている。職人さんが自ら売らなければいけない状況にあるのです。しかし、職人さんには販売のノウハウもなければネットワークもありません。せっかく作った良い商品が在庫として眠っていたんです。その理由のひとつが価格の問題です。良い商品であっても高ければ売れない。この状況が続いてしまうと廃業を迫られる生産者も増えてしまいますし、売上を作らなければ後継者を育てることもできません。結局、価格に関係なく、良い商品が生活者や使う人の手に届くような流通構造を作らなければ根本的な問題は解決しないのではないかと考えました。それならば、従来の流通に代わるような新しい流通構造を当社で作りたい、頑張っている生産者の役に立ちたいと考え、3年くらい前から構想を練っていたんです。」

しかし、アイデアはあっても堀田氏一人で進められるものでもない。そこで声をかけたのが、『JAPAN BRAND PRODUCE SCHOOL』の第1期生で、合同会社Catal代表社員の浦田修伍氏だった。堀田氏のアイデアと思いに賛同した浦田氏は、共にあらたなビジネスを立ち上げることを決意する。こうして設立されたのが、伝統工芸品の和食器のサブスクリプションサービス『CRAFTAL』である。
2019年6月、『CRAFTAL』は飲食店向けサービスとしてスタート。2020年5月からは家庭向けサービスも開始し、順調に契約数を伸ばしているという。

『CRAFTAL』が生み出した思いがけないメリットが、
生産者や飲食店の意識改革にもつながった
現在、『CRAFTAL』が提携している産地は、小石原焼、唐津焼、有田焼。美濃焼、京焼・清水焼、益子焼、瀬戸焼、新潟漆器、信楽焼、笠間焼、江戸切子、江戸硝子のほか、連携作家の作品となっている。また、『CRAFTAL』の存在を知った生産者から提携を希望する声も増えているという。
「当初は、これまでのコンサルやプロデュース事業で知り合った生産者さんに声をかけたのですが、サブスクリプションサービスに対してネガティブ反応が多かったのも事実です。『ただでさえ商品が売れない状況なのに、レンタルされるともっと売れなくなるんじゃないか』と。そういう反応のかたたちにしっかり伝えたのは『単なるレンタルサービスをしたいのではなくて、新しい流通を作りたいんです』ということでした。」

『CRAFTAL』では和食器をリースするだけではなく、気に入った商品を購入することも可能。また、飲食店のオーナーが顧客に販売することもできる。小さいながらもあらたな流通が生み出されている。さらには、『CRAFTAL』によって生産者や飲食店にあらたなメリットも生まれているという。
「これまで生産者は自分たちが作った和食器が、どういうお店で使われているのかを知る由がありませんでした。そこでわれわれが、ご契約いただいた飲食店に食事に行き、『こういうふうに使われている』と写真を撮り、シェフの言葉も添えて送るのですが、とても喜ばれるんですよ。『自分が作った器が、東京の代官山にある、こんなすごいお店で使われているのか』と(笑)。それは職人のモチベーションにもなりますし、次の商品作りのインスピレーションにもつながっているようなんです。一方、飲食店側からも、『新しい料理のインスピレーションがすごく湧きます』とか『器が変わることで、お客さまが喜んでくれる』などの声をいただいています。」

当初は、都内の飲食店のみだった契約者も、名古屋、神戸、博多、三重県といった地方にも少しずつ拡大している。
「この『CRAFTAL』という事業が拡大することが、生産地にとって流通の出口を増やすことにつながる。それによって産地貢献になっていくと思いますし、次の世代に日本の伝統文化をつないでいくことにもなっていくと思うんです。まだまだ小さな貢献でしかありませんが、多くのかたに共感していただきながら続けていくことが大切だと感じています。」
前例のない唯一無二のサブスクリプションサービス『CRAFTAL』。勇気を持ってこの事業に乗り出した株式会社Culture Generation Japan。小さく始まった動きは、多くの共感者を呼び、大きなうねりとなる日が来るかもしれない。そうなってほしいと思わせる事業である。