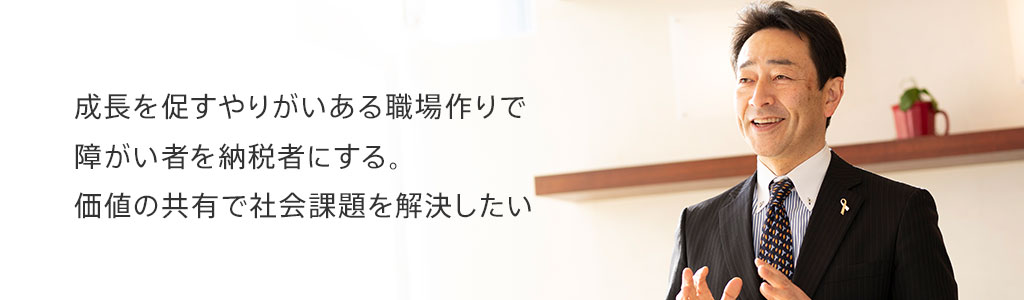ストーリー
仙台市郊外にある「自然派ビュッフェレストラン 六丁目農園」は、野菜中心の手作り料理で連日満席の人気店。その従業員の7割が障がい者だ。地元企業の株式会社アップルファームが運営し、福祉と収益を両立する事業所としても注目を集めている。開店3ヶ月後に起きた東日本大震災を機に、民間の立場から障がい者就労支援への注力を志した。そのノウハウと理念を広める取り組みについて、代表取締役の渡部哲也(わたなべてつや)氏に聞いた。
障がい者が成長できる会社を作ろう
「自然派ビュッフェレストラン 六丁目農園」は、高速道路のインターチェンジの側、田畑と工場が広がる立地にあり、ランチのみの営業にもかかわらず1日150人が来店するという人気店だ。店内には季節の野菜を中心に、石窯ピザ、自家製の豆腐などの手作り料理が並び、スタッフが生き生きと働き、楽しげに食事をするお客さまで賑わっている。この店の約40名の従業員のうち7割が、何かしらの障がいをもっているのだそうだ。

今から9年前の2010年11月、このレストランから「障がい者雇用の実現」への挑戦が始まった。きっかけは、義弟の交通事故だった。後遺症の高次脳機能障害で感情のコントロールができない義弟は、就労もままならず、高齢になる両親が介護をしていた。その様子を見ていた渡部氏は、障がいをもつ人が自立するにはどうすればいいのかを考えるようになった。
「福祉のことはまったく知らない状態でした。障がい者就労支援といっても自分に何ができるかわかりませんでした。」
2009年、渡部氏は、当時自身が経営していた小さな鯛焼き店で、発達障害のあるひとりの青年を雇い入れてみることにした。初日、その彼は鯛焼きを素手で掴んでお客様に「ほい」と渡した。自分のことを延々と話し続ける、すぐにさぼる、無断欠勤をするなどで、仕事どころではなかった。ところが、日々繰り返し一緒に働くことで変化が現れた。鯛焼きを焼かせてみると仕事に集中するようになり、お客さまにいらっしゃいませ、ありがとうが言えるようになった。当時34歳の問題児が、3ヶ月という短い間に戦力となったことに驚いた。
「そうだ、障がい者が働ける職場を作ろう。」
渡部氏のスイッチが入った。改めて福祉事業所を見学してまわると、障がい者に簡単な作業しか与えられていなかった。工賃も低く自立どころではない。
「障がいがあるからといって単純作業しかさせてもらえなければ、つまらないし、長続きしない、成長もしません。自分の実力よりもレベルの高いことを繰り返しやることが成長に繋がることを、鯛焼き店で目の当たりにしたのです。」
食品輸入会社の経営から飲食業に入り、さまざまな業態の店舗を運営してきた渡部氏。民間企業の経営者として人を教育してきた経験もある。一人ひとりが自分のできることを分業すればチームで勝てるという仮説を立て、「自然派ビュッフェレストラン 六丁目農園」をオープンした。初代の窯焼きピザ職人を務めたのは、鯛焼き店の彼だった。
「これで私たちも安心しました」
彼の両親の言葉は、今も心に深く刻まれている。

再生ビジネスで、社会の課題を解決
「このビジネスには3つの再生があります」と渡部氏は言う。
1つめは、居抜き物件の再生。公団が所有するこの建物は空き物件になって3年が経ち不良債権化していた。約50社が物件を見に来たが、ここでビジネスをする自信はないと借り手がつかなかった。渡部氏も自信があったわけではないが、ひとりでも多くの雇用を創出するためには広い場所が必要だった。
2つめは、農家で捨てるしかない規格外の野菜を手間ひまかけて調理・加工していること。農家の収入を安定させ、店の付加価値を生むことができる。
そして3つめは、働くことができない環境に置かれていた障がい者を戦力化することだ。

「障がいをもつ人を見ていると、不得手なことがふたつありました。ひとつは接客。もうひとつは臨機応変な対応です。苦手を排除して勝負できる業態を考えた答えがビュッフェレストランでした。」
ビュッフェならオーダーを取らなくていい。メニューや水を出さなくていい。お客さまの好きなものをセルフサービスで食べてもらえる。11時15分の開店時間に合わせて段取りをすればいいため、臨機応変な対応は少ない。
障がい者を雇用したレストランは、開業当初からテレビなどのメディアにも取り上げられ、お客さまが行列を作るほど忙しくなった。開店したばかりの店を普通に運営するだけでも精一杯。障がい者支援どころではなく、本当に無理をさせている状態になり、健常者からは「障がい者をこき使っている」と非難されることもあった。渡部氏自身も非難を受けて当然だと思っていた。しかし、当事者である障がい者の意識は違った。
「辞めるどころか、大変だけど楽しい、やりがいがあると言ってくれたんですよ。彼ら・彼女らがいないと店がまわらないので頼りにしている部分もありました。誰かの役に立てることが大事なんだということがわかったのです。」
飲食業には、焼く、切る、洗うなど、いろいろな仕事がある。アップルファームでは、レストラン以外にも自社農園や清掃などの職種もある。現在は、農家やホテルなど人材不足で困っている外部の事業所の業務請負をするなど、障がい者の雇用を創出している。
「まず、できることを探します。その人の優れた部分と業務上で必要な能力は違います。障がいの特性と業務に必要なことをマッチングさせることが重要なのです。特性を見つけたら繰り返し練習します。健常者が1週間でできるようになることを、障がい者は3年かけてできるようになるかもしれません。ひたすら信じて忍耐強く待つことです。」
人が組織に合わせるのではなく、組織が人に合わせる。午前中は薬の影響で頭がボーッとするなら、午後からの出勤にすればいい。相性が悪い人がいるなら顔を合わせないシフトを組んで徐々に馴らしていけばいい。少しの工夫で働けなかった人が、働けるようになることもある。型にはめないことが大切だ。とはいえ、渡部氏にとってもビュッフェ業態の運営は初めて。障がい者雇用も、大人数で働くことも初めてだ。まさに試行錯誤を繰り返しながら、この9年間で延べ200人の障がい者を雇用してきた。一緒に働くことで得られたノウハウは今、障がい者就労支援ビジネスに取り組む大きな財産となっている。

福祉と収益を両立、民間の力で社会貢献
開業から3ヶ月後、東日本大震災が起きた。津波は店の目の前の駐車場まで達したが、高速道路が防波堤となってレストランは奇跡的に被災を免れた。「自分は生かされたとすごく感じました。生かされた者の責任として、自分の役割が何かを改めて見つめ直し、障がい者就労支援事業を推進していくことを強く心に誓いました。」

震災で店舗営業ができない期間が1ヶ月以上あり、再開したときは従業員と渡部氏も働くことができる喜びを改めて感じた。しかし、障がい者は震災とは関係なく、社会の理解がないために、または偏見によって仕事をさせてもらえない。機会さえあれば、働きたい人はたくさんいる。震災後、働ける人をひとりでも多く増やすために、理念とノウハウを広める活動をしていこうと渡部氏は心に決めた。
「障がい者を納税者にする」は、アップルファーム設立時からのミッションだ。障がい者の経済的な自立を支援することを意味している。現在、日本には障がいをもつかたが約930万人いるが、実際に働いているのは49万人にすぎないという。もしもっと多くの障がい者が就労できれば、日本の人手不足は改善できるのではないだろうか。税収が減っていく中、今まで国のサポートを受けていた立場の人が国に納税をすることができれば社会貢献度は高いのではないだろうか。障がい者の就労支援は、日本の社会が抱える課題の解決策になると渡部氏は考える。
「企業は公器だと、昔から日本で言われてきました。しかし、戦後は利益優先になり本来の公器ではなくなってきています。震災復興は日本のよさに立ち戻る取り組みでもあります。CSRからさらに一歩前進してCSV(Creating Shared Value:共有価値の創造)が言われるようになったのも、日本の中に公の器という考え方が再び広まってきているからではないでしょうか。企業が障がい者を雇用して収益を上げることができれば、公益性のある資本主義になります。障がい者雇用レストランはその1つの形です。」
実際に、予約が取れないと言われるレストランの人気を支えているのは、障がい者の活躍だ。
「飲食業界は慢性的な人手不足で効率化を追求してきました。冷凍食品、機械加工品、電子レンジを使って、人の手を使わない料理を出しています。しかし、私達の店はぜんぶ手作り。障がい者の活躍によって十分に人手が足りているので、手作りの料理を提供できることが最大の強みです。」
障がい者が生き生きと働く姿は、就労を希望する人にとって大きな励みとなる。アップルファームは、ハローワークの紹介や障がい者の両親からの推薦で人材が集まる、働きたい会社になっていた。

利他の精神で、理念をフランチャイズする
渡部氏の半生は、山あり谷ありだった。高校3年生の18歳で父が事業に失敗して破産。50億円の負債を抱えた大型倒産で、それまで何の不自由もなく育ってきた渡部氏の生活は一変した。学費を払うことも困難だったが、どうにか高校を卒業。父のリベンジをしようと、金持ちになることをだけを考えて20代を過ごした。職を次々と変えたが、瞬間的によくなっても長続きはしなかった。本当の仲間もいなかったのではないかと感じていると言う。
「二宮尊徳のたらいの水の例えをよくしますが、自分のほうに掻き寄せた水はへりにぶつかって向こう側へまわっていきます。逆に、奥へ掻き出した水は向こう側のへりにぶつかって自分のところへ戻ってきます。本当にいい経営をしている人は水を奥に掻き出していると、大人になってようやく気づきました。30代で障がい者を支援するための事業を始めましたが、実は私が支援されいろいろなことを教えられています。」

今日の社会環境は、障がい者が主役になる黎明期だと渡部氏は感じている。企業は雇用率達成の義務としてではなく、戦力として障がい者に期待し始めている。一人ひとりが活躍できる環境を作らなければ企業の存続が危ぶまれる。福祉行政にも民間的なサービスが求められ、当事者である障がい者に喜ばれない施設は統廃合するという考え方になっている。
「今後、取り組みたいのは理念のフランチャイズです。成功事例を自分だけのものにせず、世の中に広めることで、私達と同じような環境の会社が日本中に増えていくお手伝いをすることが自分の役割だと感じています。飲食業に限りません。その企業の職場に障がい者を受け入れるための仕組み作りをするために、人材育成、告知に資本を投下していきたい。」
宮城県内では、すでにいくつかの理念のフランチャイズ企業が運営を始めている。加盟店料やロイヤリティをもらうことはない。その店舗や事業所のカラーを生かした経営をしている。全国から「六丁目農園」の視察が増え、渡部氏もコンサルティングや講演にまわるようになった。これからの日本の持続的な発展を支える、障がい者就労支援ビジネスの成功モデルが、復興の地、仙台から広がろうとしている。